一般社団法人 食品品質プロフェッショナルズ代表理事の広田鉄磨が執筆した記事が、食品と科学 2021年5月号に掲載されました。月刊 食品と科学様の許可を得て、公開しております。
目次
本文紹介
日本の食品防御の課題
広田鉄磨
Hirota Tetsuma
(一般社団法人 食品品質プロフェッショナルズ 代表理事)
食品防御に対する基本的な考え方に埋設された問題点
今までのHACCPの考え方の中には、 食品防御は入っていなかったのですが、 国際的な食品安全マネジメントシステムの中には、 GFSIの提唱する食品防御の考え方をそのままそっくり取り込んでいるものもあります。
食品防御といえば一連のテロ対策のうちの最重要項目のひとつと標榜されていた時期もありましたが、 過去十数年間、 爆弾テロは頻発しても食品テロは一度も起きていません。 起きているのは個人による意図的な混入ばかりです。 危害要因分析では【危害の重篤度】と【起こりやすさ】を掛け合わせた尺度でリスクを評価しますが、 同じ尺度の上では、 個人による意図的な混入の【起こりやすさ】が食品テロの【起こりやすさ】をはるかに凌駕するといえます。
個人による意図的な混入を食品テロと取り違えて錯綜している人も後を絶ちませんが 個人による混入はあくまで個人に内在するネガティブな心情を行動の起点とし、 それに対して、 食品テロは組織的な対立構造を行動の起点としている点で大きく異なるのです。
過去には日本の食品防御では監視カメラに傾斜した投資が行われてきましたが、今据え付けられているカメラ群は本来の設置の目的であった、 個人による意図的な混入の抑止というよりは、トラブル発生時の従業員の動線や機器操作が適切であったか否かを後日チェックしてみるなどのレビュー可能な動画記録としての貢献のほうが大きくなっているのではないでしょうか。
以上述べましたように、 テロと個人による混入の定義面での混同、 さらにはリスク評価の尺度の上でテロと個人による混入が無差別に配置されている点が日本の食品防御におけるリスク評価を攪乱させている元凶といえましょう。
食品防御に関するガイドライン群
様々な食品防御にかかわるガイドラインが上梓されていますが、 リージョナルな広がりをもって参照されている文書を抜き出すと、 イギリスではPAS96、 アメリカではFSMA食品安全強化法、 グローバルな展開ではWHO文書、 日本及び日本向け商品を製造している中国では厚生労働省支援事業食品防御の具体的な対策の確立と実行検証に関する研究成果物が挙げられます。
イギリスPAS96
PAS96は英国規格協会が提唱している案ですが、 公開仕様書というレベルであって規範としての効力はまだ持ち得ず、 しいていえば参照文書といってよいでしょう。
筆者が読み取る範囲で、 PAS962017年度版の特徴を以下に示します。
- 2010年度版に始まるTACCP (Threat Analysis CriticalControl Point) という手法の有効性の強調があります。 当初TACCPについて2ページを費やしていたものが2014年度版以降では3ページに増え、 TACCPの概念から派生する他項を含めると2014年度版以降はTACCPという単一概念の上に全文を構築しているようにもみえます。
- 2014年度版以降では意図的な混入に経済的動機によるもの (食品偽装) も含んでいます。
- 犯人像の想定とその性格描写に多くの字句を費やしています。
- 特に第3の犯人像の想定はこのようになっています。
- (利益を目的とした企業などへの) 脅迫犯人
- (露見を恐れる日和見的な)内部犯行者、 または (納期に間に合わせるために時々混ぜ物をしたとしても別に露見しないだろう、 というような日和見的な) サプライヤー
- 過激集団・単一意見に傾斜した集団
- 不条理な (精神に問題をもつ) 個人
- (組織が不公平であると信じ復讐を追い求める) 不満を持った個人
- ハッカー
- プロの犯罪者集団
イギリスで過去に頻繁に起きた事件での犯人像がすべて網羅されているのかもしれませんが、 すべて悪意が前提となっています。 日本でよくある、 犯罪が露見して後に 「なぜあんないい人がこんなことを?」 「魔が差したとしか思えない」 といった、 性弱説でしか説明できないような、 なにかがスイッチを押したために簡単にハードルを越えて犯罪者となってしまう、 偶発的な犯罪者ともいえる存在についての補足説明が、 日本でこの文書を採用するためには必要なものとなるでしょう。
アメリカ食品安全強化法
食品安全強化法はアメリカの国内法であり、 運用はアメリカ国内に限定されるべきところです。 しかしながらもFSVP (Foreign SupplierVerification Programヒト及び動物の飲食に供するための外国供給業者検証プログラム) によってその裁量権を国外にまで伸展しているため、 アメリカへの食品輸出をする事業者に対しても食品防御方針に関しての影響力を及ぼしています。
食品安全強化法の規則の中に 「意図的な食品不良事故からの食品防御のための緩和戦略に関する規則」 が含まれており、 JETROによる和訳では、 次のようになります。
パート121-意図的な食品不良事故からの食品防御のための緩和戦略 セクション
サブパートA-総則
121、 1 適用性
121、 5 の免除のいずれかが適用される場合を除き、 本パートは、 米国内で消費する食品を製造・加工、 梱包または保管し、 連邦食品医薬品化粧品法415条により登録を義務付けられた国内または海外食品施設の所有者、 運営者または代理人に適用される。
ここにあるように、 アメリカ国内での産品に限らず、 アメリカに輸出する事業者もすべて対象になり、 その事業者における食品防御の実施状態は 「ヒト及び動物の飲食に供するための外国供給業者検証プログラム」 によっての検証の対象となるわけです。
しかし 「意図的な食品不良事故からの食品防御のための緩和戦略に関する規則」 はHACCP (つまり食品安全) での要求事項をそのまま食品防御に転用したと思えるものばかりであり、 以前 Focused Mitigation Strategies To Protect Against Intentional Adulteration, Proposed Rule 2013「意図的な異物混入に関する2013年規則案」 に見られていたようなFDAによる集中緩和策・広域緩和策の区分は消えさり、 民間の意見を尊重し、 HACCPと同様、 食品防御は事業者自らが考え、 構築するものとして締めくくっています。
研修についてはFDAとイリノイ工科大学が共同で設立したFSPCAFood Safety Preventive Control Alliance が担当していますが、 この原稿を著している2021年3月時点であっても、 Preventive Controls for Human Food First Edition-2016 がテキストの最新版であり、 その中では食品防御計画に始まるパート121-意図的な食品不良事故からの食品防御のための緩和戦略に関する項目は見えません。 別途、 食品防御に関する研修が編成されていますが、 Preventive Controls for Human Food の研修プログラム中には取り込まれていないということは、 刮目して見るべきものです。
以上を包括して言えることは、 アメリカ自身が食品安全強化法の施行を受けて、 国内での対応に追われている状況であり、 食品防御の具体的な方針についてはまだまだ議論のさなかにあるということです。 そのため、 食品防御に関してアメリカの主導が外国に及ぶまでには、 まだまだ期間を必要とするといっていいでしょう。
WHO文書
グローバルレベルの文書であるWHOTerrorist Threats to Food, Guidance for Establishing andStrengthening Prevention andResponse Systems, 2002 ですが、 微生物及び放射性物質の脅威を大きく取り上げているという点では他の追随を許しません。
食品テロの実例として挙げられるのは、 1984年アメリカで起きた反社会的な宗教集団による751人の患者を出したサルモネラ菌混入事件だけであり、 他に引用されているのは個人による意図的な混入あるいは偶発的な混入、 または経済的な動機による混入事件となっています。 また、 偶発的に起きた食中毒事件に対して 「もしもその事件が仮にテロリストの手によるものであったとしたら?」 という極端な演繹を行い (現実離れしたストーリーであっても)、 万が一それが起きた場合には注意すべきという警告を発しているにすぎません。
実際には、 食品の加工には殺菌工程が含まれることが多く、 殺菌工程があれば病原菌のほとんどは死滅してしまいます。 また、 食品は他の原材料と混ぜられてのち最終製品となることが多いため、 混入した毒物は希釈され、 急性毒性量を維持することは非常に困難となることについての補足が必要かもしれません。 原材料での汚染が、 そのまま減少することもなく消費者のもとに届くことは、 起こり難いといえます。
食品企業で対応可能とされている対策群は、 アメリカの食品安全強化法で要請されている対策群とほぼ同様の現実的な内容にとどまっています。
日本厚生労働省科学研究事業成果物
研究班の成果は平成23年度 (2011年) 発行の 「食品工場における人為的な食品汚染防止に関するチェックリスト」 「食品防御対策ガイドラインについて平成23年度版」 として結実しました。 このガイドライン序文では、 次のようにテロの脅威が強調されていました。 食品テロというものが 本当に身辺で いつ何時でも起きうるという前提のもとに全文が構成されています。
はじめに2001年9月11日に米国で発生した同時多発テロ事件を契機に、 世界各国でテロの発生に関する認識が高まり、 テロ対策は、 国家防衛上の優先的課題となっている。 わが国では、 1984年のグリコ・森永事件、 1998年の和歌山カレー事件、 2008年冷凍ギョーザ事件等が発生しているが、 これらは健康被害をもたらすことを意図して食品に直接有害物質を混入したものであり、 実際の被害の発生範囲は限局的なものであった。 しかし、 フードサプライチェーンの過程で有害物質が混入されれば、 被害の発生範囲が拡大することは容易に予測される。
中 略
米国では、 災害やテロ等に対する国家全体の応急対応計画である 「National Response Plan」 において 「食品テロの危険性」 が明記される等、 国家の全体の安全保障における 「意図的な食品汚染」 の位置づけも明確にされている。 わが国でも、 従来の食品衛生対策に加え、 意図的な食品汚染行為を防止するために、 「組織マネジメント」 「従業員等の管理」 「部外者の管理」 「施設管理」 「入出荷等の管理」 等の実施により、 より積極的な食品防御対策を講じる必要性が高まっている。
中 略
米国FDAによる 『食品セキュリティ予防措置ガイドライン食品製造業、 加工業および輸送業編』 は、 フードサプライチェーンが食品への有害物質混入等悪意ある行為や犯罪、 テロ行為の対象となるリスクを最小化するため、 食品関係事業者が実施可能な予防措置を例示し、 現行の手続きや管理方法の見直しを促すために作成されたものである。 その対象は、 農場、 水産養殖施設、 漁船、 食品製造業、 運輸業、 加工施設、 包装工程、 倉庫を含む全ての部門 (小売業や飲食店を除く) である。 今回、 米国のガイドラインを参考に、 わが国の実情や、 複数の食品工場での実地調査の結果を踏まえ、 食品工場の責任者が、 食品工場における悪意を持った者による意図的な食品の汚染行為を防止するためのガイドラインを作成した。
序文中ですでにテロと個人による混入が錯綜して語られ、 この文書の目指すところを不明確にしてしまっています。
次の平成25年度 (2013年) 版ガイドラインでは、 新規にWHO文書、ISO文書が取り込まれたこと、 優先度に応じた対策という実装化への努力も見えなくはありません。
その後も 「食品防御の具体的な対策の確立と実行検証に関する研究」 という名目で、 科研費に基づく作業は毎年継続しており、 奈良県立医科大学の公衆衛生学講座のウェブサイトに、 2021年1月20日アップロードで最新版 「令和元年度 食品防御対策ガイドライン」 (案) が掲載され、 その中身を見ると、
- 従業員教育の際には、 内部による犯行を誘発させないよう、 部署ごとに応じた内容に限定する等の工夫や留意が必要です。
- 従業員への教育では、 具体的な事例や方法を伝えすぎないように注意することが重要です。 教育用媒体を有効に活用しましょう。
人間関係が大事と冒頭に述べているにもかかわらず、 いまだに極端な従業員不信が見られる点を除き、 以前に比べると Employees First へ向けての大きな歩み寄りを見せています。 しかし、 今のところ厚生労働省が積極的にこのガイドライン(案) を取り上げているという気配はありません。
過去には平成23、 25年度版ガイドライン中に示されているものの中でも、 特に監視カメラ、 認証システム、 私物持ち込みのチェックなど、 数値化しやすい、 あるいは有り無しで白黒の付けやすい項目を優先した取り組みが積極的に推奨されました。 ハードとしても新規性を持っていたため、 消費者へのアピールとなると事業者側でも判断されたのでしょう、 瞬く間に日本は監視カメラ大国へと変貌を遂げていった感がありました。 これとは別に、 人が一番大事であるという Employees First に近い概念を提唱した企業群もあったのですが、 それらの声はかき消されてしまったようです。
食品テロの技術的制約
以前、 全アメリカを震撼させた文書として、 もし牛乳にボツリヌス毒素が混入されたら数十万人の犠牲者を出しかねないという科学論文があり、 これこそが食品防御の熱狂の引き金となりました。 その後、 スイスの研究者よりボツリヌス毒素の耐熱性は想定されたほどではなく、 牛乳の殺菌工程でほとんど無毒化されて、 そのような被害は起きえないと反駁されています。
あるグローバル企業から提唱されている概念として Band Width (バンドウィヅス被害の広がり幅またはパターンとでも訳すべきか) というものがありますが、 食品テロとして大きな被害を引き起こすためには即効性の毒物を選ぶのは自然な流れといえましょう。
テロリストがその目的を達するためには、 一回の消費で一気に成果を上げる必要があるからです。 逆にいえば、 毒物の選択肢は即効性でなければならないという点で 非常に限定されているということになります。 そして即効性の毒物でありつつも、 致死量を超える混入量で 「無味無臭」 =つまり喫食にあたって異味異臭に気づかない…というものはさらに限定されます。
大規模テロに使用する食品は、 目的とする地域に一斉に配送され、 遅滞なく消費されるものでなければなりません。 なぜならば、 犠牲者発生というニュースが流れたとたんに消費者はその食品の購入を停止し、 毒物混入済商品の多くは回収・廃棄されてしまうからです。
消費者の購買停止が間に合わない、 回収・廃棄が追い付かない即時配送・即時消費を実現しているのは牛乳しかないといわれています。 牛乳でいえば、 酪農家から製品出荷までの全段階について全面的な食品防御を施すことは現実的には難しいですが、 工場からの出荷時の官能試験を強化するといった対策をすれば、 テロリストの計画の多くを簡単に挫折させることができます。
ほぼ無味無臭の感染性食中毒菌を使用したバイオ食品テロの可能性もいまだに声高に唱えられることがありますが、 食品製造ラインには殺菌工程が組み込まれていることが多いため、 それが生物兵器としての効果を激減させてしまうことになります。 また殺菌工程以降で混入された菌であっても、 食品の栄養組成がその菌の栄養要求にマッチングしていない限り、 菌は死滅曲線をたどり始め、 こちらも効果を激減させてしまうことになります。
そのため、 微生物を使用しての食品テロは、 消費に近いところで危害の混入を行わなければターゲット集団に対して致命的な症状を引き起こすという目的を達しえないということになります。 「消費に近いところ」 という原則に忠実に従ったものが、 戦後の歴史で唯一ともいえる食品テロである1984年アメリカ・オレゴン州でのサラダバーへのサルモネラ菌混入事件です。
この観点からは、 食品テロは集会などでターゲット集団が同一の食品を短時間にほぼ同量ずつ消費しうるような条件が設営された下では再発も考えられるといえます。 また、 ターゲットを限定できるというのは、 テロが成立するための重要な条件であるともいえます。 どのテロ集団も、 自派にあるいは自派の支援者に大量の犠牲者が出ることを望むはずもなく、 犠牲者の多くを対立集団に限定するはずです。
(食品テロに対峙した形態である) 個人による意図的な混入というものは、 特に人間関係の荒廃した職場で起こる可能性が高く、 職場を熟知した従業員による犯罪なので、 犯人は当然、 検知システムの裏をかくはずです。 そのため、 分析担当は何を分析したらいいのかの予備知識を全く持ちえず、 必要な分析機器を事前にスタンバイしておくことは難しいことになります。
相手はラインを熟知しているのですから、 金属探知機があればガラスをというように、 検知の裏をかく方向に出るため、 ラインに常設されている検知機器の有効性は期待できません。
このような検知体制にあえて引っかかるような異物を混入するのは、 犯罪者の中でも非常に衝動的であって、 自分の犯罪が露見することまでに思慮が回らない犯罪者、 またはあえて露見させることで自分の不満を表明するといったメッセージ型犯罪者に限定されるのではないでしょうか。
化学物質でいえば、 人による官能検査が (致死量水準の毒物であればほぼすべて) オールラウンド・オールタイムで検知可能な唯一の手段となります。 しかしながら犯人が、 商品価値の棄損程度あるいは企業の信頼度の凋落あるいは流通の部分的な混乱程度を達成期待水準とするのであれば、 官能検査に引っかからない程度の化学物質 (アレルゲンを含む) の混入にとどめることは大いに考えられます。
こういった低濃度の混入では官能検査もまた無力となっていくことが避けられません。 官能検査で検知されなかった混入製品は市場に出ていき、 例えば犯人による通告によってはじめて混入の事実を知るわけで、 その後の公告と回収の実施での企業の負担は深刻なものとなるでしょう。
低濃度の混入をも抑止の対象とするのであれば、 事業者としてできる対策は、 職場環境の改善、 従業員の満足度の向上、 そしてその結果として (外部よりの侵入者をも含めて) 自分たちの職場を破壊するような行為を許さないという連帯感の育成に至っていくこととなります。
人による人の行為の抑制、 つまり犯罪者の心理そのものに集団として働きかけ、 犯罪の芽を未然に摘むことを目指すのが選択肢となっていくのです。 何をどの程度混入されるのか想定できないような環境下では、 検査機器・分析機器・測定機器といったハード面での対策はほぼすべて無力化されてしまい、 機器設置は費用対効果の観点からはまったく無駄な投資でしかないからです。
おわりに
いま日本に求められるのは、 現代的な性善説とも言ってよいものに違いありません。 昔から日本は性善説と主張するグループもありますが、 日本に生まれたすべての人間が生まれつき善性であったというわけがあるはずもなく、 個々人を善行動に向かわせるための集団的な規範が、 一定期間適正な状態に維持され、 風土とも言ってよい社会的な調和状態を生み出していたというだけに過ぎないのではないでしょうか。
集団的な規範というものは、 戦時中の忌まわしい記憶から忌避されがちで、 (最近では) 自粛警察であるとか、 いびつな行動が社会を混乱させているため誤解を受けがちです。 本来は法に頼ることなく、 社会が自らを自らの手で律していくことです。 法律というものはアップデートにも難があり、 またその解釈にも大きな変動幅が付きまといます。 それに対して集団的な規範というものは、 時代の変化に柔軟に対応が可能で、 いちいち国会を通す必要もありませんし、 解釈に当たっても、 法律家の意見を待つような必要もありません。
働くことは悪という西欧的な固定概念と異なり、 日本にはいまだに勤労を善きものとする社会的な風土が生き残っています。 社会風土が健全に維持されているなら、 それはそのまま (自分にとっては幸福を追求するのに大切な、 勤労を提供する舞台である) 職場を守りたいという個人としての心情に変容しうるものです。
会社が従業員の幸福形成に積極的に関与し、 会社の気配り・思いやりを従業員が深く認識するのであれば、 職場が自分の幸福を生み出すための大事な舞台であることを認識することにつながり、 その職場を守りたいと願うようになるのは当然の心理的な帰結です。 自分の職場を守るために、 柔らかな相互監視体制が形成され、 職場から不心得者を出さない、 職場には不心得者を侵入させないという連帯意識が生まれ、 それは強力な抑止力として機能するものとして期待できます。 アメリカではこれを Employees First とし、 概念の見える化を図っていますが、 日本では標語やスローガンまでの必要性は薄いのではないでしょうか。 時に触れ、 折に触れ、 みんなで職場を守ろうという意識付けの機会を共有することで十分ではないでしょうか。


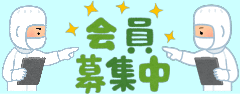
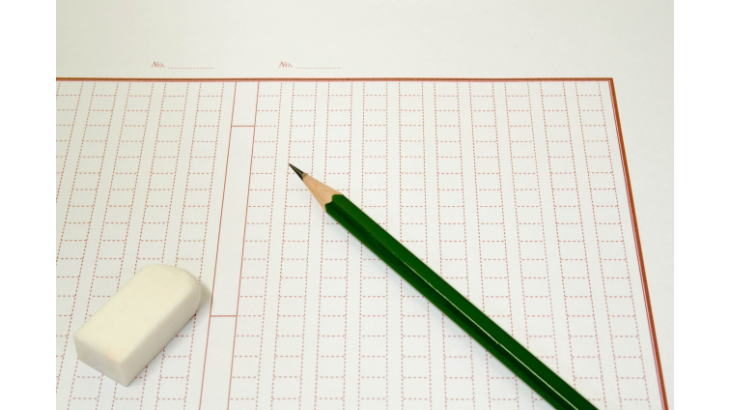

![改めて食品防御・食品偽装を考える(6)[月刊アイソス]](https://qpfs.or.jp/wp-content/uploads/2023/02/isos2303-730x410.jpg)