一般社団法人 食品品質プロフェッショナルズ代表理事の広田鉄磨が執筆した記事が、食品と科学 2021年7月号に掲載されました。月刊 食品と科学様の許可を得て、公開しております。
本文紹介
書評:なぜ社会は分断するのか ~情動の脳科学から見たコミュニケーション不全~
著者 伊藤 浩志
発行所 専修大学出版局
定 価 3,080円、 四六判、 312ページ
評者 広田鉄磨 (一般社団法人 食品品質プロフェッショナルズ 代表理事)
まず私自身、 長年リスクコミュニケーションを今後どうすべきか悩んできたので、 この本で取り扱われているテーマが非常に身近なものに感じられたのが、 この本を手にとってみようという気になった動機といってよい。 例えば、 食品添加物などを使用する合理性を訴求する際に、 ①科学的な議論に軸足をしっかりおいて感情論に流されぬようにするように、 ②傾聴に代表される態度、 反対論者の意見に耳を貸し、 決して頭から否定しないように、 ③反対論者の裏には扇動者がいるはずで、 その扇動者をこそまさにたたくべきといったファクトチェック方式、 そして私自身もその信奉者だが、 ④コミュニケーターが反対論者から見て信頼できる、 親近感を持てる人でなければ説得の成功はおぼつかない など多種多様な 「説得」 のアプローチが存在している。
しかしながら、 伊藤の著作を読んでみると、 私たちの①から④までの行為は、 すべて対立構造のギャップは説得によって埋めることができるという 「甘ったるい」 期待の上に成り立っていることが明白となる。 これまでのリスクコミュニケーションは、 「感情的になると理性は働かなくなる」 とする理性中心主義を暗黙の大前提にし、 正しい科学知識を身につけることで、 過剰な不安を解消することを第一の目的としていた。 それに対して伊藤は、 最新の脳科学の知見から、 「感情がなくなると理性は働かなくなる」 と説く。 事故や脳腫瘍などの手術、 病気で脳にダメージを受け、 不安を感じることができなくなってしまった人は、 理性は正常でも、 合理的な意思決定ができなくなり、 望まない、 自分が不利になる言動を平気で繰り返すようになる。 危険を無意識のうちにいち早く察知する不安という情動反応は爬虫類にもあり、 長い生命の進化の過程で大切に保持されてきた命を守るための警報装置なのだ。 科学的には一見不条理に見える消費者の過剰な不安も、 人間が自然界にあって、 自分の身の回りにある危険を敏感に嗅ぎ出して、 自分の身を守ってきたからこそ現在の繁栄があることを思えば、 情動反応の 「過剰さ」 は人類にとっては大切な欠くべからざるものであることがわかる。 これまでの科学的リスク評価は、 過剰な不安の背後にある生物学的な合理性を見逃してきた。 このことが、 科学技術をめぐるコミュニケーション不全の主要な原因になっていることを、 伊藤は数々の事例を挙げて検証していく。
現代社会の繁栄を導き出してきたものが、 個人の富の追及であり、 他者に対する優位性の追求であることは明白であって、 このカルチャーを一朝一夕に変えていけるとは私は期待しない。 しかし、 不平等が社会的な弱者ばかりか社会全体にも不安をもたらし、 不安はサイトカインの放出を招き、 心身に悪影響をもたらすことは疑いもなき事実である。 通常は可処分所得の上昇⇒医療水準の向上⇒寿命の延伸という風なポジティブなサイクルにはまって平均寿命は延びていくのであって、 確かに高所得の国ほど寿命の延長が見られる。 しかしながら、 可処分所得がある程度のピークに達したのちはその国における社会的な不平等が寿命の延伸を阻害しはじめ、 「勝ち組」 を含めて、 それ以上に寿命が延びるか否かは、 まさに社会としての平等感の醸成にかかっていると伊藤は述べる。
第三章である 「科学は 『公正中立で客観的』 という幻想 人は心地よい解決を求めるのであって、 正しい解決を望むのではない…」 は秀逸であって、 科学者もまたバイアスから逃れることはできないことが語られる。 我々は今まで科学と感情の二元論を前提とした議論に明け暮れてきたが、 すべて脳という情動で動作している器官が我々を突き動かしているのであって、 二元論の形をとりながらも実はその間に明確な境界はない。
人は社会性を持つことで繁栄し、 社会性の醸成とともに、 さらにまた脳が発達するというサイクルを経て、 動物界では体重当たりでは最大の脳を持つようになった。 この進化の方向にあらがうことはできないであろう。 人類の社会性というものが異質なものの排除であるとか、 異質なものとの対立であるとかではなく、 相手を認めあうことによって成し遂げられてきたことを伊藤は諄々(じゅんじゅん) と語っていく。
この本を読んでみて、 初めて北欧などで成功しているといわれるリスクアセスメントに関する対話集会 (西欧でも全くの失敗に終わったという意見もいただくが) が、 ①適切な人数でパネルを組み、 ②長い時間をかけ、 ③何度も何度も会合を繰り返し、 ついには 「コンセンサス」 (と我々が甘ったるい期待感を込めて呼ぶ) に至るのは、 要は人間が繰り返される対話というプロセスを通じて相手方を同じ社会を構成するメンバーであると認識し始め、 お互いにメリットのある方向性つまり対立を生まない共存の方向性に落としどころを求めるからなのであろう。 対して、 国や科学者がフクシマに関してのリスクアセスメントの説明を住民に対して行ったとしても、 ①~③までの内容には欠落が多く、 ましてフクシマに居住していない人間が短時間の間に何を言ったとしても 「同じ社会を構成している一員」 として認識してもらえるわけもない。 さらには国や科学者が二元論に縛られた説明を行えば、 それは住民との距離感を広げることにしか機能しないのではないだろうか。
久しぶりに骨のある書籍を手にした気がする。 闇夜を照らす一灯といってよい。 諸兄諸姉に推薦したい。
ダウンロード

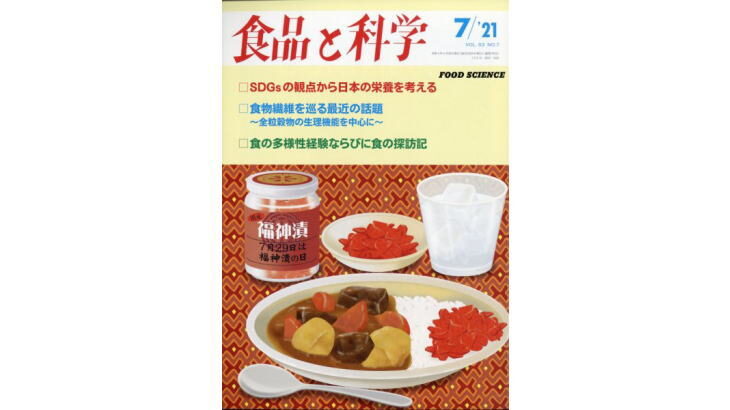
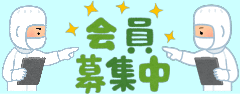
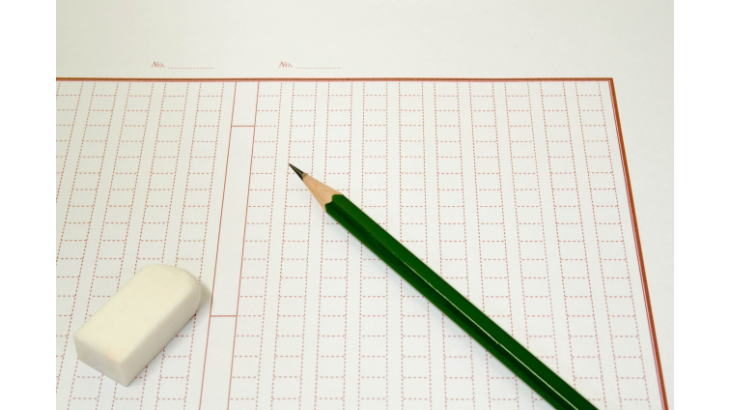

![改めて食品防御・食品偽装を考える(6)[月刊アイソス]](https://qpfs.or.jp/wp-content/uploads/2023/02/isos2303-730x410.jpg)
![改めて食品防御・食品偽装を考える(5)[月刊アイソス]](https://qpfs.or.jp/wp-content/uploads/2023/01/isos2302-730x410.jpg)