(一社)食品品質プロフェッショナルズ 古川 哲也
鰹節HACCPの構築に関連してヒスタミンの情報収集に行ってきました。シンポジウムで発表された内容の一部と、里見正隆先生による大変参考になった講演の一部を抜粋させて頂きました。
1.延縄(ハエナワ)漁法で漁獲をすると、どの時点で死んだかが把握できないので、海水温が高く、縄の回収までの時間が長いとヒスタミン蓄積の可能性がある。漁獲時の履歴(海水温、作業時間、水揚げ後から凍結までの時間、凍結温度他)がしっかりとトレースができる原料を使用しなければヒスタミン食中毒の発生リスクは高くなる。魚の加工場における低温管理、低温加工は重要であるが、元々の魚原料に問題があればそれらの努力の意味がなくなる。
以下、延縄漁法についてです。
<延縄漁法>
夜明け前4時頃に投縄に入ります。投縄作業は全長100~150kmもの長さの幹縄に目印となるブイや縄を浮かすためのフロートを付けます。また、約3,000本の枝縄と釣り針に、早業で イワシ・ムロアジ・イカ等の餌を付けていきます。この投縄作業に約4~5時間を要します。投縄作業は当番制で、だいたい、2~3日に1回の割合で順番が回ってきます。
一方、揚縄(水揚げ)の作業は、基本的に全員が協力して行ないます。揚縄は、マグロが餌にかかるまで3~4時間を縄待ちした後,ウインチを使ってマグロを縄ごと回収する作業です。揚縄作業は10~15時間かかり,ときには、深夜まで続くこともある重労働です。釣上げられたマグロは、船上で体長を測り、エラと尾を切り離し、はらわたを抜いた後、-60℃で急冷します。そして、船の冷凍庫(-55℃)で長期保存され、その後、焼津・清水・三崎などで水揚げされ、流通を経た後に消費者の元へ届けられるのです。
2. ヒスタミン研究で難しいのは、腐敗=ヒスタミン産生でないこと。冷蔵庫保管をしており、腐敗していないが、ヒスタミン産生する事がある。
3. ヒスチジンが、マサバ(1,291ppm)、マイワシ(964ppm)、真鯛(560ppm)、ゆで大豆(476ppm)に存在するものを絞ったドリップを測定したところ、遊離ヒスチジンはマサバ(800ppm)、マイワシ(900ppm)、真鯛(10ppm)、ゆで大豆(3~10ppm)であった。マサバ、マイワシの様にこれだけ遊離ヒスチジンが多いと、簡単にバクテリアに食べられ、ヒスタミンに変化していく可能性がある。真鯛はヒスタミン産生魚種ではないが、擂り潰したものを原料にすればヒスタミン産生もあり得る。
4. 普通にヒスタミン産生菌は鮮魚に付着しており、海洋・陸上由来細菌の両方で汚染されている。ガンマ線滅菌(35kGy)をした魚(マグロ、かじき、ぶり)を5℃、15℃、25℃に保管してもヒスタミンが産生しない結果がでている。ヒスタミンは魚肉由来ではなく、やはり細菌が関係している事が実験により確認できた。
5. マグロのブロック(4cmの立方体)にヒスタミン産生菌を植え、どのように増えるかを確認したところ、3~5日経過後、植え付けた箇所から5mm程度までは増え、1~2cm離れると増えていない事が分かった。意外とヒスタミン産生は広範囲に拡散しない事が確認できた。飲食店等で切身の提供をしたものから、ヒスタミン食中毒になる人とならない人が出る事があるが、単にヒスタミンに対する感受性の他、部位差による影響もある。サンプリング場所で全く結果が異なり部位差が大きいので、規制値が立てにくいものである。
私は水産加工工場の品質管理に携わった経験があります。その経験から判る事なのですが、ヒスタミン管理を徹底しようとしてもすぐに壁が現れ、先に進めなくなるという現状があります。
例えば、冷凍魚の証明書類を仕入先に要求した場合、以下の様なものが入手出来ます。
<国内産 魚原料>
船名、水揚げ港、漁獲海域、水揚げ時期、動物用医薬品情報(養殖魚)、放射能検査結果
<外国産 魚原料>
船名、水揚げ港、漁獲海域、水揚げ時期、動物用医薬品情報(養殖魚)、インポーター、パッカー、通関証明
これらの内容では、原料の安全性を確認できる事は困難です。市場経由で漁業者に細かい事を要求すると、「あー、面倒臭いな。そしたら他の市場に下すから、買わないでいいから」と言われる場面が容易に想像できます。漁業者は良くも悪くも、細かく、面倒な事はしたくない、言い方を変えますと小さな事には拘らない気質があります。市場がHACCP対応、EU輸出対応に意識が変わり、それに伴い漁業者も徐々に変化をしていくと思われます。その様になるまで、加工業者はロット毎の抜き取り検査で対応するしか方法がないのでは? と感じております。
水産加工工場できる取り組みとして、原料面では、上記記載の証明書類の他、「転売を繰り返した様な冷凍原料を購入しない」、「証明書が速やかに出る様な先から購入をする」、「ロット毎にヒスタミン検査証を要求し、社内でも抜き取り検査をする」かと思います。加工面では、「低温(5℃以下)で加工し低温保管」、「保管期間は数日(3日程度)に留める」、「下処理に関しては、頭、エラ、内臓、うろこを除去し、水道水でしっかりと洗浄する」かと思います。根本的な解決には、漁業者の考え方が変わる事が必須であり、早い時期に意識が高まる事を期待したいものです。
最後に、公益社団法人日本食品衛生学会 シンポジウムにてご講演された、国立研究開発法人 水産研究・教育機構 里見正隆先生の「ヒスタミン産生菌の生態とその制御」に非常に興味深い内容が含まれておりましたので、読者と共有したく、一部抜粋させて頂きました。
<ヒスタミン産生菌の制御法>
食品の種類によりヒスタミン生成菌の種類は大きく異なる。そのため、ヒスタミン生成菌の防除法も食品によって異なる。生鮮または加工度が低い食品では主にグラム陰性菌が、発酵・熟成を伴う食品では主にグラム陽性菌が制御の対象となる。
<生鮮食品におけるヒスタミン生成菌制御法>
魚肉中のヒスチジンがヒスタミンに変換されるため、醗酵や酵素製剤による筋肉タンパク質分解などの処理を行ってヒスチジンを遊離させない限り、筋肉中の遊離ヒスチジン含量が高い魚種がヒスタミン蓄積のリスクが高い魚種と言える。日本では漁獲・流通量が多いさば、いわし、さんま、かじき、まぐろ類などが主なアレルギー様食中毒の原因魚種として知られている。海外でもかじき・まぐろ類、シイラ、南洋性回遊魚が原因魚種として認識されている。FAO/WHOバイオジェニックアミン専門家委員会の報告書では過去にアレルギー様食中毒を起こした魚種やヒスチジン含量の高い魚種のリストを作成し、一般名、学名、ヒスチジン含量、漁獲量を掲載している。リストに挙がった魚種はヒスタミンを蓄積しやすいと推定されるが、あくまでもヒスチジン含量が高いということだけである。取り扱いが悪ければ低ヒスチジン含量の魚種でもヒスタミンの蓄積は起こり得る。
生鮮魚で問題となるヒスタミン生成菌は前述したように通常の海洋生物と腸内細菌科細菌である。従って、大腸菌群や腸炎ビブリオの増殖を抑制する様に対策を講じていれば問題は無い。一部のヒスタミン生成菌は低温環境でも増殖するが、ヒスタミンを著量蓄積するまでに最短で5℃にて3日かかることから、コールドチェーンを徹底し、加工工程でも温度管理が行き届かない時間帯を無くすことが重要である。FAO/WHOバイオジェニックアミン専門家委員会でもHACCPの徹底で制御可能なリスクであると報告されている。つまり、ヒスタミン蓄積の予防は通常の食中毒防止活動を実践する事で大切である。かじき、まぐろなど、延縄漁で漁獲される大型魚の場合は、延縄に掛かってから船上に揚げられるまでの履歴が曖昧で、海水温によりヒスタミン蓄積が懸念される。最近の研究では、海水温31℃の場合、10時間以内ならヒスタミン蓄積のリスクが少ない事が報告されている。
<発酵・熟成を伴う食品におけるヒスタミン産生菌制御法>
魚醬油、チーズなどの発酵食品では、ヒスタミン生成菌が原料に混入し、発酵中に有用常在菌とともに増殖し、ヒスタミンを生成すると考えられている。魚醬油などの水産発酵食品では、原料魚と食塩を混合したもろみに好塩性のヒスタミン生成乳酸菌が混入することでヒスタミン蓄積が起こることが明らかにされている。防除策としては、工場内の洗浄と発酵スターターの利用が挙げられる。ヒスタミン生成遺伝子は種を超えて伝播する為、野生株のみでヒスタミン生成菌の増殖を抑制する事は難しい。そのため、ヒスタミンを生成しない発酵スターターの使用が推奨される。共同研究グループは市販の大豆醤油用発酵スターター株や魚醬油から分離された増殖活性の高い株をスターターとして魚醬油発酵時に添加する事で魚醬油中でのヒスタミン蓄積を抑制している。また添加したスターターが良好に発育できるよう、スターターの栄養素となる糖質(グルコースやショ糖)を副原料として添加することでスターターの増殖が安定することも見出した。一方、ヒスタミンの蓄積は、もろみ中に混入した少量のヒスタミン生成菌により引き起こされることが明らかにされているため、工場内に棲みついているヒスタミン生成菌を洗浄により排除することも有効である。実際、ヒスタミンの蓄積が頻発していた加工工場で、工場内の徹底洗浄、スターター添加および発酵原料の改良を行ったところ、アミン類の蓄積を抑制することに成功した。このように発酵・熟成を伴う食品の場合は、工場内の洗浄を繰り返し、発酵スターターを有効利用するなど、制御法を組み合わせて根気よく、ヒスタミンの蓄積を抑制していく必要がある。
以上
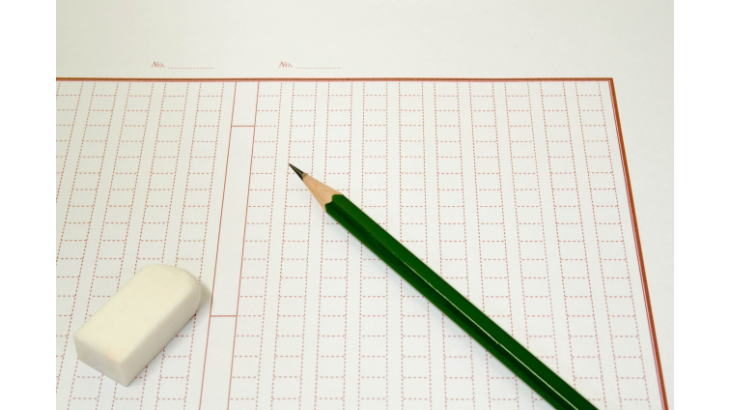
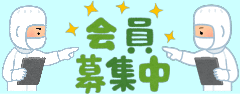

![改めて食品防御・食品偽装を考える(6)[月刊アイソス]](https://qpfs.or.jp/wp-content/uploads/2023/02/isos2303-730x410.jpg)