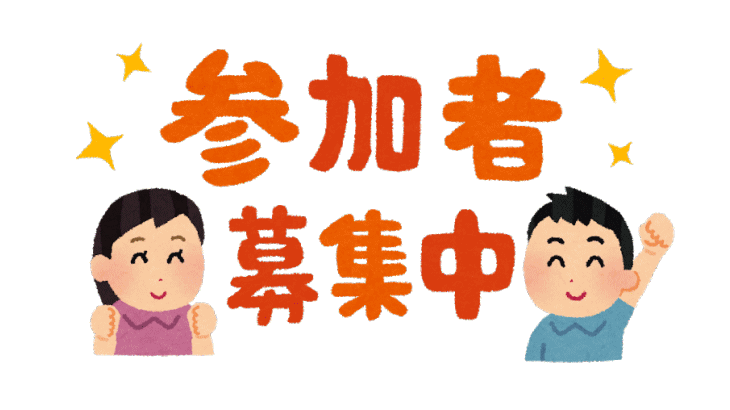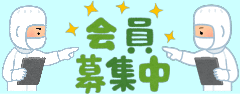ポイント
いままでヒューマンエラー対策といえば 毎日注意喚起をすれば何とかなる、ダブルチェックすればミスは防げるといった古典的な考えにのっとったものが大半でした。しいて言えば 労働密度の適正化、照明の最適化、騒音の制御などで 人がエラーを起こしやすくなる環境を改善していけばいいというところまでがせいぜいでした。しかし 現在ヒューマンエラーと呼ばれているものは 本当にすべて人間が引き起こしているのでしょうか。単にエラーが起きた場所に たまたまそこの担当者がいただけだったということはありませんでしょうか。こういった根本的な疑問をシドニー・デッカーの学説「人はエラーを引き起こす存在でもあるが 同時にエラーや事故の発生を未然に防止している存在でもある」という観点からレビューしてみます。 工場で労働安全の担当でもあった講師・広田鉄磨は 何か事故が起きるたびに追加される安全器具・保護具がかえって事故を誘発してはいないかという疑問を持ち続けていました。ヒヤリハットが300件あれば、小さな事故が30件起き、そのうちの1件は重大事故につながるという ハイン・リッヒの「法則」というものが実際の工場の状況にはうまくあてはまらないという感触を持っていました。ヒヤリハットが起きている事実がちゃんと共有され、真剣にその対策が協議されている職場環境であれば 事故にはつながっていないのではないかと。
これをシドニー・デッカーは安全文化という言葉を使って明確に説明します。今回のセミナーでは いままで当然のように「法則」として語られ、ヒヤリハットが多ければ必ず重大事故が起きる、だからヒヤリハットを最小限にすることが唯一の方策であるとまでいわれて 強制力すら持っていた「法則」が 単なる歴史上のある時点、それも安全文化など存在せず 人が積極的に事故防止に関与していなかったころの「観察」にすぎず、安全文化が浸透しつつある現在では まったく別の視点が求められていることを解説します。
プログラム予定
- ヒューマンエラーと呼ばれているものの正体は?
- 人はエラーを引き起こすこともあるが それはまれであり 通常は何かのエラーが事故につながっていくことを未然に防止している つまりコントローラーとして機能している存在である
- スイスチーズモデルの欠陥:いくら安全装置を重ねていっても どこかに抜けができる
- AI化、コンピューター化を最終的で完璧な安全装置と期待している向きもあるが 所詮は人間の設計したアルゴリズムで動いているシステムでしかないので 低率とはいえ必ずエラーを起こすものである
- エラーが安全装置を潜り抜けていることを察知して それに対応できるのは人間しかいない
- つまり 人とシステムの緊密な連携を行っていってこそ エラー防止、事故防止が成り立っていく
- 人とシステムの連携の中には 人と人同士の連携も入っており ここでのグルー(接着剤)として機能するのが 安全文化に他ならない
- 自社事例をもとにQ&A
日程
2025年12月15日(月)
時間
10:00~14:00
途中1時間の昼食休憩。持ち込んでいただく質問が多ければ 最長で16:30まで延長可能
場所
千里山コミュニティセンター
〒565-0844
大阪府吹田市千里山霧が丘22-1 BiVi千里山3階
阪急電車を千里山駅で降りて東側すぐ、30秒でつきます。阪急オアシスの入るビルの3階です
料金
- 16,000円(税込)
- 紹介コードあり 15,000円(税込)
- 会員またはその代理 13,000円(税込)
定員
最大15名
主催
講師
広田 鉄磨、他 一般社団法人 食品品質プロフェッショナルズ認定講師
お申込み方法
お申し込みは締め切りました。たくさんのご参加、ありがとうございました。
テキストダウンロード
食品品質プロフェッショナルズではこのほかにも様々なセミナーをご用意しております。
![2025年12月15日 ヒューマンエラーと呼ばれるものの撲滅のために[大阪]](https://qpfs.or.jp/wp-content/uploads/2020/09/kenshuu-730x410.gif)