代表理事の広田鉄磨が執筆した記事が、食品と科学 2019年11月号に掲載されました。月刊 食品と科学様の許可を得て、公開しております。
冒頭紹介
はじめに
この稿を手に取られる方々の反応は大きくいって2通りにわかれるだろうと思います。第1のグループは「そんな(ありふれた)もん興味ないわ!」と相手にもしてくれない方々・・・そうです、熱殺菌(された食材)といえば、私たちの周囲にあまりにもあふれかえっています。多くの人たちは、熱殺菌という工程は電子レンジのようにモノを置いてドアを閉めてボタンを押せばタイマーが回り、チンッとなったらドアを開けるとそこには熱くなったものがある・・・誰にでも操作できる簡単なもののような印象なのでしょう。しかし、その簡単であるはずの電子レンジ、どうして発熱するの? とか、どうやったら均一に加熱できるの? とか問われてみると、誰もまともに答えられないのです。
第2のグループは「ややこしい計算式が出てきて、難しい微生物の名前が出てきて・・・(そんなのいやっ!)」と、戸惑いを顔に浮かべられる方々です。過去に熱殺菌工学をちょっとかじった方々でしょう。そのとおり、熱殺菌工学には計算式が出てきます。ラテン名というなじみのない呼び方で微生物が語られます。しかし、そういう方々も、ロカボやオーガニックやら健康にいいといわれるものについては、難しい原理やら、専門用語にでも積極的に飛びつきます。熱殺菌といえば自分が勉強しなくても、誰かほかの人が知らないうちにやってくれるもの、あえて自分の頭や手を煩わす必要もないと思うような話題になってしまっているのではないでしょうか。
つまり熱殺菌は、あまりにも日常的なものであるため関心がもてず、自分が何をしなくても、他の誰かがうまくやってくれている、そんな他人にお任せの構図が頭の中に出来上がっているのでしょう。実は私もN社という企業で、熱殺菌の指導に当たってくれという任命を受ける前は全く同じような感覚でした。「開発及び製造担当として熱殺菌した製品を扱っているのだからお前が適任!」といわれても「なんで俺にそんな退屈な仕事を言いつけるのか!」と不満たらたらだったものです。
しかし、そのような感覚は配置転換を前に改めて本を買って読み下し、図書館にこもって専門書を読み解いている間にどんどん変わっていきました。つまり熱殺菌というものは、人類が食中毒で多くの人命という犠牲を払いながら一歩一歩と知識を積み上げていき、18世紀に缶詰技術、20世紀になってアセプティックの商業化と、やっとの思いで結実させていった成果物であることに気づいたからです。偉大な先人たちの伊吹が聞こえてくるような感動に「ありがとうございます。皆様のおかげで現代の人類は、安全でおいしい食品をくちにしております」と感謝の念を口にしたほどです。
数百年前から50万年とも200万年前ともいわれる人類の火の使用開始時期までさかのぼり、私たちの生活にとって「火」つまり熱殺菌用の熱源はかけがえのない存在でした。火種を絶やさない(あるいは人類の歴史でごく最近となってからは、その場ですぐに火を起こせるという)ことは、充実した食生活のいとなみに不可欠でした。食材を焼くのか、煮るのか、蒸すのか、いぶすのか、まずは安全に食べられるように「火」をもって加工し、次いでおいしく食べようと人間は「火」に真剣に取り組み、そこから最大限のメリットを引き出そうとしていたのです。「火」は熱源であり、熱源利用の主たる目的は熱殺菌です。
食の加工の分野では産業化が進み、家庭での熱の使用は極小化していっています。私たちの日常生活において、自ら「火」を使用して食材の殺菌を行うというシーンは、とてもまれになろうとしています。ガスくらいはまだしも「火」のイメージをもっているでしょうが、電子レンジやIHにいたっては、あれが「火」という実感を持っている人は稀ではないでしょうか。しかし、だからと言って熱殺菌の重要性が薄れていっているわけではないのです。単にその場面が家庭から工場や飲食店に移ったというだけで、相変わらず熱殺菌は私たちの健康生活の維持に大きく貢献しています。
この稿では、このように我々が人類として長い間かかわっている熱殺菌をできるだけ平易な文章で、妥当性確認・検証に焦点を当てて説明しています。長い人類の歴史、その当初から人類に幸いをもたらすものであり、時には不幸をもたらしてきた「火」という素晴らしいがしかし、反面厄介なもの。その厄介なところの手綱をうまくとり、いいところばかり引き出そうと、我々の祖先が努力を重ねてきた、先達の功績の集大成のひとつが熱殺菌工学なのです。
つづきはこちらからダウンロード
後編はこちらから


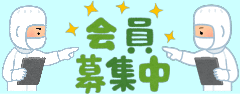
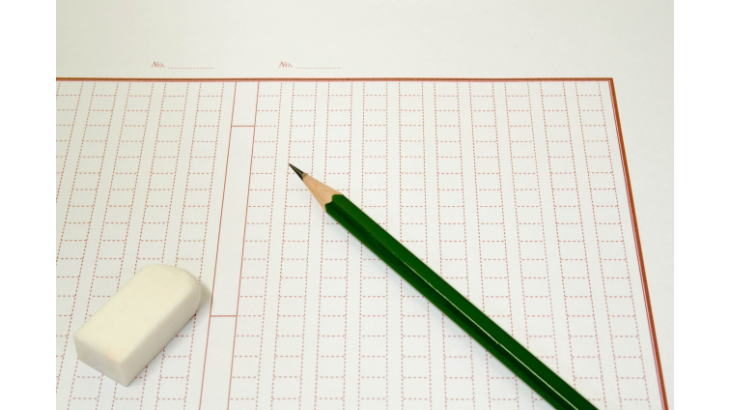

![改めて食品防御・食品偽装を考える(6)[月刊アイソス]](https://qpfs.or.jp/wp-content/uploads/2023/02/isos2303-730x410.jpg)